自分のことを『自分自身が』大切にする、という例として、
見春屋を作ったきっかけのことを話してみようと思います。
日付だけで見れば今日、3本めですね。
たくさん書いてすみません(笑)(^◇^;)
私が『見春屋』という場を設定したきっかけは、
当時、ブログ等でご縁があって話を聞く機会があった人たちのうちの数名が、
みごとに『2つの方向』にきっぱり分かれた求め方を、されて来たから。
ひとつは「このままではイヤだから、自分が変わるきっかけになるような
気づきのための、気持ちの整理をさせてほしい」
という方向に、なっていったのもの。
もうひとつは、それとはまったく違っていて、
「こんなに苦しい私のことを、大切に扱ってよ。
私が正しくて、良くて、けなげで頑張っていて、
それを認めない相手のほうが、ひどくて悪くて間違ってるってことに、
あなたが同意してよ!」
というふうに、なっていったものでした。
ふたつめの例では、私がとくに同意をしなかったので
最後には脅されたこともありました(^◇^;)
ともに、だいたいメールやメッセージでのやり取りで
(いちばん最初の人は途中から、音声でのやり取りも加わっていったのですが)、
どちらの方向の方に対しても、私がしたのは『質問』だけです。
間違ってる、なんて言葉は、ひと言も発しておらず、
主に、そのときあなたはどう感じましたか。
相手の方の反応はどうでしたか、を尋ねただけでした。
当然、私の元へ最初に送られてくる情報は、限定的になっています。
こちらへの質問の形のメッセージなので、そりゃそうです。
あとのほうの人の質問内容はとくに、
人と人の間で「発生するもの」、についての質問のみが多かったでしすし、
どちらのタイプの方々も、自分の情報を私に対して
フルオープンにされていたわけではないのです。
で、後のほうパターンでは、たとえばあるひとりの方の場合、
コメントもつくことはなく、たまにペタがつく程度、の関係。
なのでメッセージをいただいた段階で、
ご本人がブログに書かれていたことも、当然、
私は全部に目を通していたわけではありませんでした。
でもどうやら、その後のほうのある方は、
私がその人のブログにすべて目を通していて、
自分のことを「傷んでいるかわいそうな方、という見方をしてくれてるはず」
そういう前提で話されていたのだと思います。
そうでないと、あのような急な怒りにはならなかったと思えるから。
そして、自分の『味方』になる人だと、私のことを勘違いされていたようなのです。
そのときの、その方のテーマであったらしい、
自分と他者の間で起こっていた『勝ち負け』についての、
その方の主張に、私がすでに賛同しているもの、と、
思われていたのだろうか……と(後からですが)、感じました。
私は、その方がどこまで、ご自身のブログにその話を書かれてもいるかも、
まったく知らなかったのですが(今でも知らないままです)。
で、確かにその方は、傷つかれ、傷んでおられる様子でした。
でももし、だからと言って、私がその方の言うことを、
その方が望まれるがまま、賛同し、褒めたたえ、
その方にとっての『勝ち負け対象の相手』のことを、
一緒になって、けなしたら?
はい、たぶんスルリと、依存関係スタート、だったでしょう。
ことあるごとに、私を助けてよ! が始まっただろうな……と思います。
私を中心に扱ってよ、私を間違ってないと言ってよ、
私はこんなに傷んでいるのだから、
私を大切にいたわるの、当然でしょう!?
と。
もし、私がそれを最初は仕方ない、と受け止めたとして。
これが続くと、やがて私も気づいていって、
ならばあなたは、私を自分の賛同者にして、何を得ようとされていますか?
と、いつか、対応せざるを得なくなったでしょう。
なぜなら私も自分のことを大切にしたい、ひとりの人間だから、
誰かに対する『従者』の立場はいずれ、どうしたって無理になるわけです。
自分が、苦しくなる。
実際にはそんな事態にまでは至りませんでしたが、
代わりに、命令にも近い懇願が届きました。
そこに漂っていたのは、
「こんな種類のブログ活動をしているあなたが
なぜこちらのことを大切に扱わないのか!」という怒り。
その気持ち自体が
自分の中のどこから湧いているのか
を、その方は一切、気づいておられなかった、という感じでした。
そして相手(この例では、私ですね)が悪いからだ、ということに執着され、
その立場に立ち続けるために、常に私から見て『かわいそうな人』のポジションを、
この方は保ち続けざるを得なくなるだろう……と、感じました。
ほかにもきっと、こうした主従関係って、起こりえるのだと思います。
親から子に対する、
恋人に対する、部下に対する、
『私が立派と、間違ってないと認めなさい!
そうでないと私はあなたに、愛情、
あるいは思いやり、あるいは許可、
その他を示してあげないわよ!』という交換の脅迫、あるいは一方的懇願。
はい、求められても、それは私の役目ではないのですよ、残念ながら。
私は第三者という立場を貫き、質問を投げかける人であり、
これこれ、こういうことがあった、と聞いたとき、
その内容を真摯に聞きつつ(そう、先に開示していただくことが
とうしても『前提』となる)、それについて
「あなたはどう感じましたか、相手の反応はどうでしたか、
そしてそれをまた、あなたはどう捉えましたか」と、
お尋ねしていく人、なのです。
そのことは、話を聞きますよ、とブログに初めて書いたときから、
それこそずっと、述べているポイントでもあります。
でも残念ながら、たまたま、その以前の方の場合は、
その『私は第三者』の部分、スルーされておられたようなのです。
理由はわからないけれど、見逃されていた……。
で、私の例に話を戻すと。
私自身は、こりゃまずい、依存を求められても、
トラブルになるだけだと思いました。
で、私は、最初のタイプである、私に対し「整理をさせて」と言ってくれた人に
私の会話の進め方について尋ねて確認したり、
他の優秀なカウンセラーさんに直接、相談をしてみたのです。
その結果、ボランティアで話を聞くことの限界、をはっきり知ったのでした。
ときに、私の『質問』が刺さる場合。
それをボランティアでやると、
その質問自体がなかったことにさえ、されてしまったり、
そんなことは聞いてない、と『自分に都合の良い部分でだけ、
自分に同意する』ことを望まれてしまう……。
その可能性がはっきりしました。
それでは、私が『自分のために、ご自身が捉えてみてほしい』
と願っている気持ちとは、まったく違うところへ展開してしまいます。
ということで、そもそもの部分をスルーされないようにするために、
きちんと『場所』を作って、そこに来ていただく、
つまり『自分と向き合う、というのは、自分自身でやる作業』だということを
明確に意識して、その勇気を持っていただいた方に私も問いかけできるよう、
場、を設定することにしたのです。
それが『見春屋』という形になりました。
そして問いかけする私もまた、時間と自分自身のエネルギーを、
その方に対して捧げることになるので、その部分では、
お返しとして「お金」を受け取る、つまり交換、ですね、
その交換をする勇気を私も持たねば、よい結果が生まれない、
私もまた『交換で受け取る』覚悟を、場によって求められることになったわけです。
今でも私は、ときにコメントやメッセージなどを、
こちらから勝手に送ることがあります。
その際には必ず、自分のお節介を、謝りながら。
だって気になって、言葉がけを送りたくなっているのは、私なのです。
ですがそれは、私の感じることを、私が大切にする、という面の現れだとも
自分でわかっているので、自分に許しています。
そして幸い、言葉を送った方にも、その私の意図は今のところ、届いています。
それは本当に、本当に、ありがたいことで、感謝しています。
あなたの問題は、必ず、あなたが自分で越えられます。
答えは必ず、あなた自身が知っていて、
それを受け容れる「タイミング」になったときに、
自身で気づいていけるのだと、今の私には思えています。
あなたは、誰かのために存在しているのでなく、
誰かに認めてもらうために、生きていかねばならないわけでもありません。
相手の方もひとりの、ある「やり方」や「価値観」を持った人間ですが、
あなたもまた、ひとりの、
かけがえのない、世界で唯一の、大切な存在です。
あなたとその人は、同等であり、別々の人間であり、どちらも大切な存在。
相手が輝いてもいいのと同様に、
あなたもまた『独自に自分の内側から』輝いていいのです。
だから、相手と同じにならなくても、
つまり感覚が一緒でなくても、別にいいのです。
そのことに気づく勇気を、どうかいつか、持ってください。
この言葉が必要な方に届きますように、という願いをこめて、
この記事を、上げさせていただきます。
 Photo by PublicDomainPictures
Photo by PublicDomainPictures
Pixabay

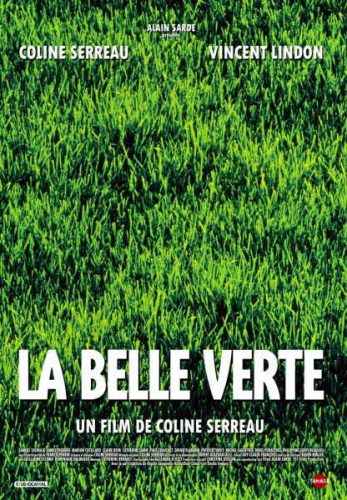
 Photo by PublicDomainPictures
Photo by PublicDomainPictures