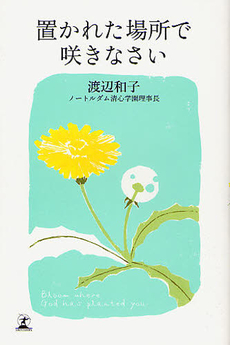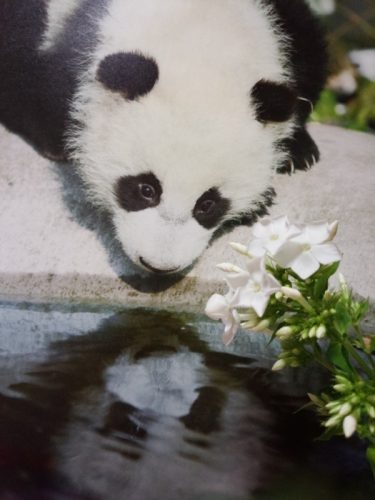これはとくに、がんばってきた人、
あるいは「他人が怖い」人に向けての話……だけれど。
この2つはぜんぜん、違うものであるようでいて、でも実は、
その根っこには同じ部分があるのかも……と思えている。
何が同じかというと「自分を何かしらの方向で、良く見せたい」という願望の部分で。
もちろん、あなたにはもともと「良い部分」がある。
今の段階では、それを「信じられない」人もいるかもしれないけれど
もし万が一、100%悪人、っていう人がいるとすれば、
そもそも「がんばろう」とか「他者の目が」なんてこと、
気にしない……と思えるのだ。
だってたぶんそういう人って、本気で自分の都合しか考えないから。
他者を気にする、ということや、自分を自分でなんとかしよう、と思えること。
それは「他者のこと」をちゃんと意識し、考えられる人、ってことなんだと、
私には感じられるのだ。
で、こうした人たちに共通するのは
先ほども言ったように「良く見せたい」(良くなりたい)という願望、かな、と思う。
でもそれって行き過ぎると「見栄」につながる。
この「見栄」が、扱いを間違えると「自分に嘘をつく」ことになる……。
過去の自分を振り返ってみたときの経験もふまえ、そう思えるのだ。
強がり、意地っ張り、その反動としての「後から湧く」自己嫌悪。
見栄を重視し過ぎて、本当に自分が望んでいること、を超えて、
自分に無理をさせたり、自分を「ごまかしたり」する。
それはやがて「望んでもいない自分」を演じようとすることにつながる。
なぜなら、それをはるかに超えても気づけなかったり、
逆に「できない」と決めつけて怯えさせたりするから……。
ゆえにそれが、やがては「自分に嘘をつく」ことへつながる。
「望んでないもん!」って意地をはって「求めるものを見ないように」したり、
「もっともっともっと、きちんとできないと!」って、
すでにできてる部分まで「自分で見えなく」したりする。
今、現在、できていようと、できていなかろうと。
そもそも、そこまで完璧に、できなくていいのよ。
「いい加減」は「良い加減」でもあって、
できなさ過ぎるのも、でき過ぎるのも「度を越している」ことになる。
その「見栄」、そこまで必要じゃない。
必要だと「思い込んで決めつけている」のは「今の」あなた自身であって、
そう決めつけていることが「今」、まさにあなたを苦しくする。
実はそれ、ちょっとでいいの。少しずつでいいの。
やらないより、やったほうがマシ。そんな程度。
もう一度繰り返すよ、過ぎたるは及ばざるがごとし、なのだから、
やらなさすぎも、やりすぎも、「度を外れている」って意味では同じ。
だから、やりすぎる人がやってない(怖くてできない)人を
見下したりバカにするのも、実は違うし、
やってない人が「『やってる人』ってきっと、私をバカにしているに違いない」って
勝手に決めつけ、すねるのも、ある意味、失礼だよね。
少なくともその相手は「すでに実際、チャレンジをがんばっている人」なんだし、
そこですねたら、まるで逆恨みしているようにも、見えてしまうかもしれない。
ねえ、まずは、自分に「嘘」をついたり「ごまかし」をすること自体、やめようよ。
求めるのはいいことだよ、それ自体は全然、否定しないでいい。
でも、「自分で自分を『素晴らしい!』と自画自賛できるところまで」
求めすぎると、動けない、あるいは動きすぎることになる。
そんな自画自賛って、もしかしたらただの「自己満足」にすぎないのかも。
そっちを求めることによって逆に、
他者の心を「思いはかる」視点、消えちゃうのかも。
もったいないよね、そもそも今すでに、持っているのに。
怯えも、やり過ぎも、「見栄っぱり」すぎる自分がいるから。
失敗したっていいのよ。っていうか普通はみんな、
「失敗しながら」練習してる。
練習しないと上達しない部分は、確かにあるからね。
当然そこでは「失敗」(と自分が感じること)だって起こる。
必要なのは「何度、失敗してもいいから、いつか望む方向へ行こう」という
自分の思いを大切にできること、なんだと思う。
それを「開き直り」と呼んでもいいのだと。
ふてぶてしく、態度をわざと悪くするような「開き直り」ではなく
「いずれ、できるようになりたいから」の、静かな、ひそやかな決意の開き直り。
それは決して「厚かましさ」にもならないよ。
「練習の積み重ね」の原動力、につながるものなのだと思える。
だから、あきらめないで、よい意味で
「開き直って」ほしいと思う。
練習って「こうやったら、なるほど、うまくいく、あるいはいかないんだな」っていう
「方向性の確認」なのだから。
それって失敗、というより、
エジソンの言うように、1万回でも、方向性を確認してみて
「うまくいかない」部分と「うまくいく」部分を少しずつ、自分で体得すること。
だからこその「練習」なんだって、ことだと思う。
「自分が望む」段階ですでに、その能力はあなたの中に「ある」のだから、
あとは「自分が心地よい範囲で、上手に、バランスよく表現できる」方法を、
練習、するだけだよ。
ぜひ、あきらめないで、開き直りつつ、やってみてください。
いっときバカにされたように感じようが何しようが、そんなのどうでもいい。
あなたの求めるものは「その先」に必ず待っている。
練習して体得した先に「感じられるもの」は、きっと
とても素敵なあなたの「開花」になると、私には思えるから。

よい開き直りで、順番に、「本当の花」を咲かせていこう。少しずつ。