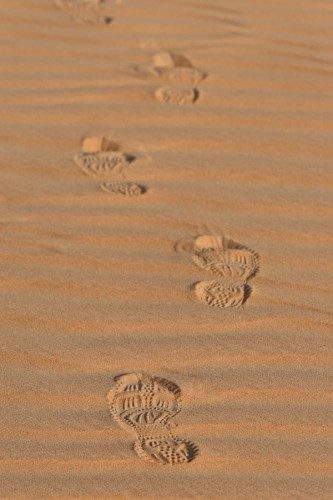今さらのように、心屋さんの『「めんどくさい女」から卒業する方法』を
古本屋さんで買って(ごめんなさい……)読む。
最初のほうでいきなり、私が夏に受けたセッションの「無限&地獄ループ」の話と
近いことが書かれていて、しかも心屋さんもそのループ状態を
矢印を使い、説明されていて、ああ、この方も本当に
ぐるぐるされてたんだな……と思えた。
共感と同時に、思いつくイメージが地獄で共通していたことに、少し笑えた。
これ、まだ全部を読んだわけではないけれど、別に女性に限った本ではなく、
自信がなくて、とか、「このテのパターンの問題が起こると
なんかうまくいかなくて、どうしたらいいかわからないのよね」という感じで、
何らかの状況に煮詰まり、それを繰り返したりもする人向けなんだろうと思える。
もちろん、鬱の人も含め……。
で、この本におけるヒントは「自分を客観視できるか」ということに
たぶん、集約されるのだろうけれど、
それを「責任」と強く捉え、今はまだそれを引き受けたくないわ、と思える人は、
この本を読んだら「何を言ってるんだよ」怒ったり、
「そんなことできるわけがない」と投げやりになったり、
「でも自分は……」とあきらめたりするのじゃないだろうか。
男女に関わらず、そう感じてしまい、読めない人もいるんじゃないかな。
要するに、自分の「あり方」を自分で決める、そういうのが怖いとか、
考え方としてキライ、あるいはわからない、と単純に捉えているのだと思う。
でも本当は、別に怖くはないことなのだ。
確かに最初は「勇気」のような感覚、もしかしたら人によっては
そういうことに近いような「切り替えのためのキッカケ」を、
自分で、自分のために作ろうとする努力は要るだろう。
努力というか、割り切りというか、開き直りというか……そういう感じのもの。
それをしたくない、見たくないから、自分の代わりに他人を支えてみようとしたり、
自分ではなく他者のほうを変えてみようとしたりすることにも、
つながるのかもしれない。
自分のあり方を変える代わりに、他人を何らかの形で意識し、
そっちのほうで何かを変えようとし、色々な理由にもして、生きていく。
それが正反対の方向に向けば「他人の拒否」にもなる。
要は、近づくか離れるか、とにかく他者との関係性のなかで、
おもに自分を何とかするほうへ注目するやり方。
本当は、自分に近づくことが望ましいのに、
そこは見たくないから……または、
まだ自分で、そこを見られないから。
でも、あくまで他者は、気づきのヒントやキッカケになるだけで、
自分のことをどう捉えるかは、自分で決められるし、決めていかないと実際、ツライ。
本来、その部分は、他者を通じてどうこうしようとか、できるものではないから……。
しかも、いったん、自分を見つめる目を切り替え始めてみたらわかるけれど、
その感覚をつかめば、切り替えていくほうが、
どんどん自分で自分をラクにしていけるし、
気づくたびに笑えるし、楽しめるし、明るくなれる。
その視点から逃げたままでいることが、
決して「悪い」わけでもないけれど(別にそんなこと、
気づくことなく生きていく人は世の中にたくさんいる気がする)、
ただ、人間関係では自分対他人、自分対自分、の面で、
疲れたり苦労することがどうしても増えるんだろうな、と。
で、その「苦しさ」というのは、まさに気づきのヒントであって、
自分でラクにもできるんだよー、ということを、
カウンセラーの方たちは、仕事として、行っているんだろうと思える。
せっかく今、ヒントを見つけるチャンスが訪れているのだから、
それを使わないのは正直、もったいないような気がする。
どんなにダメな自分でも、自分のことを「変に曲解することなく」
認められるというのは、とても気持ちいいことなのだから。
いじけたり、すねたり、自己嫌悪に陥ったりする一方で、
同時に意固地でもある、他者とのよい関係性に執着もする。
そんな苦しみ方……自分でわざわざ、人や社会や自分自身に
求めながら背を向けるようなことは、
まったく必要ないんですよ、という話なのだ。
だって本当にそうだから。
お気楽で泰平、のほほん、ウフフな面を持てるようになれれば、それでいいから。
表面的にそうなるのでなく、また、それを演じるのでもなく、
いい加減なダメ人間になるのでもなく、
本質的に、そういう部分を持つ人間で「あっていい」という話。
泰平な部分は、平穏や穏和、につながるし、それはいざ問題が起きたときに
必ず自分自身の冷静さにもつながる。
静かに、ぶれないで、ラクにいられる。
それってものすごく強い人のように、他人から見たら、思えるよね?
でも本人は「自分の弱さを知ってて、ゆるしてるだけ」なのよ。
それ以外のコツって、とくにいらないかも、とさえ思える。
今、世界的に有名な、そういうお方……と言えば、
私がまっ先に思い浮かべるのはダライ・ラマ猊下(げいか)で、
まあ、マザー・テレサもそうだけれど、
宗教家の方達は、まさに心の修業を自分に課すことになっていくから、
自然に、そうした姿勢が「目立つ」ことになるのだと思う。
でも、そこまで達観しなくても、自分をラクにする範囲で、いいのだとも思える。
それらはすべて、自分の弱さを認める、その責任を「あくまでゆるく、力まずに」
「良し悪しの判断でないところ」で受け入れる、引き受けることなんだろう、と。
これ、わかり始めるまでは、たとえば、
いい加減な人とか、理想でない自分になる、などとしか思えなくて、
そんなふうになりたくない、ダメになりたくない、という拒否感も
強いと思うけれど……。それがもうそもそも、実は違うのだ。
今すでに、自分のことをダメだと捉えているのだから、
それをそのまま、うまく「使う」ほうが、本当はラクなんだよー、という話。
抽象論ではあるけれど、実際の練習は「力んで意識し、
努力しまくる」ようなことでない。
ドキドキすることは最初に多少、あってもね。
本当に全然違う。ベクトル、向いてる方向が違うのだ、それ。
二次元レベルで右か左か、前か後ろか、みたいなことでなく、
もっと違うところ……斜め上くらいから、離れて自分のことを見つめるような感覚。
ぐるぐるしている人はある意味、視点が二次元になっているのだと思ってほしいし、
できるようになったタイミングで「立体化」してほしい……自分自身のために。
そうすればまさに、自分を自分で太陽のように照らし、
静かに穏やかに、優しく柔らかく光り輝かせることが、できるようになるのだから。
そのユルさ、ラクさ加減って、練習すればするほど、心地よく感じていけるよ。

まずは、他者に対してであれ、自分に対してであれ、
こうならなければいけないはずなのに、なぜうまくいかない?
またはやってくれないの? とかいう、その思い込み自体を
自分で丁寧に見つめてみることから、始めてもらえたらと思う。
だってそうに決まってるじゃない! という、その「そうに……」の内容を、
あなたはいつ、なぜ「そう決めた」のだろう? というところから。
世間の常識とか、他者の目や評価などが大前提になって
ただ「決めつけ」てはいないかな? 本当にそういうこと、やってないかな?
それが苦しいのは、自分の感覚には合っていないからじゃない?
では、その「自分の感覚」って、どんなものだろう?
……そんなふうに、捉え直して、見つめてみてほしい。
誰かの本や言葉が、あなたにとってよいキッカケになることを祈ります。